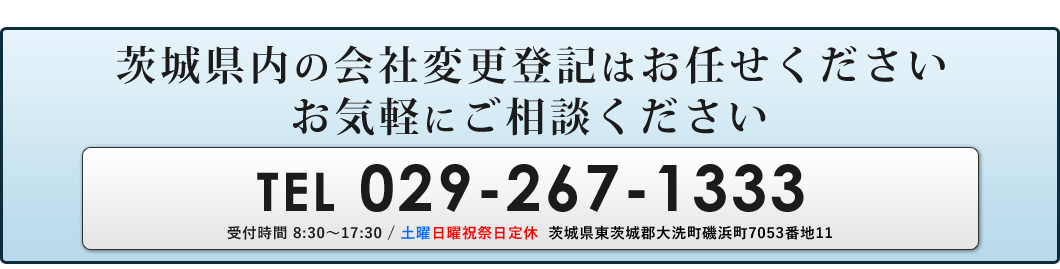会社登記の用語解説
会社と法人とは
会社とは、株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社などの営利法人を指します。
合名会社と合資会社は歴史のある会社にみられる形態ですが、社員が無限責任を負うため現在はほとんど設立されていません。
また有限会社は廃止され特例有限会社として株式会社と同様の扱いとなり、現在、会社の立ち上げには、株式会社と合同会社のどちらかで設立することになります。
法人とは、一般社団法人、一般財団法人、公益法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、管理組合法人、農事組合法人などの非営利法人を指します。
民法では、個人と比較するのに、上記の会社と法人をあわせて、法人と表現する場合もあります。
会社の登記とは

会社の登記とは、商取引をする場合、その相手方となる会社の存在性や商号、本店所在地、事業目的、代表者の氏名住所等の情報を確認し、安全な取引ができるようにするために、国(法務局)が会社の内容を公示する登録制度です。
会社は登記をしてはじめて法人格を取得し、取引の相手方になることが出来ます。
会社の登記は、定款の重要な事項と役員に関する事項なとが登記されることになります。
会社設立後、登記事項に変更があった場合は、2週間以内に登記しなければなりません。
定款とは

定款とは発起人(会社を作る人)が会社設立時に作成するもので、会社の事業目的、株式、運営機関、運営方法に関する根本規則(会社の憲法)のことです。
役員の員数や任期の期間、選任方法も定款に規定されています。
設立時に公証人の認証を受けたものを原始定款といい、これは会社の設立開始の定款という意味になります。
取引先の要望で会社の定款を提出する場合、定款に変更があったにもかかわらず、原始定款を提出してしまうと、現行の定款でないものをを提出してしまうことになりますので注意が必要です。
会社設立後に定款の変更があった場合は、会社自身で定款を改訂していき、会社自身が定款を保管・管理していくものになります。
法務局で取得する登記事項証明書(会社登記簿謄本)とは別なものなので、法務局で定款は取得できません。
会社役員、株主とは
会社役員とは取締役が業務の意思決定をする役員、代表取締役は会社を代表する役員のことを指します。
この取締役、代表取締役は会社の登記事項であり、法務局にある商業登記簿に記載され、役員に変更又は任期が満了したら必ず役員変更登記をしなければなりません。
株主とは会社の所有者(オーナー)のことで、株主総会において取締役、監査役を選任・解任する権限を持つものです。
株主は登記事項ではなく、法務局にある商業登記簿には記載されません。
よく誤解があるのは、株主に変更があった場合に会社の変更登記が必要と勘違いしてしまうことです。
株主の変更については、会社登記の変更は不要で、会社保管の株主名簿の変更をすればよいのです。
株主名簿とは

株主名簿とは、会社設立時に作成するもので、株主の情報をまとめた名簿です。 会社法で作成が義務付けられており、作成して企業に保管するだけでなく、税務署に法人設立届出書を提出する際にも必要です。 株主等に変更があった場合には名簿を更新する必要があります。
会社の変更登記の際には株主総会議事録を作成しますが、併せて株主リストも必になりますので、会社の株主名簿をここで確認します。
株主名簿を作っていない場合は、便宜的に確定申告書別表2の同族会社等の判定に関する明細書から現在の株主を確認します。
取締役、代表取締役とは
取締役とは会社の経営に関する意思決定をする機関名です。
取締役1名の場合は、1名が意思決定をすればよく、取締役2名以上いる場合(取締役会)は合議で意思決定します。
そして代表取締役とは、取締役が合議で決定した意思決定を、会社を代表して相手方と契約締結する権限をもつ代表の取締役になります。
社長、副社長、専務、常務とは
先ほどの取締役、代表取締役は会社法の必須の機関です。登記上も誰が取締役で、誰が代表取締役かは取引する第三者には重要なことなので登記事項になります。
しかし、社長、副社長、専務、常務は会社法の規定にはなく、登記事項ではありません。
なぜなら、これらは会社の内部の序列を表す役職だからです。会社法で規定する意味はないのです。
会社法と登記法では第三者を保護するためにありますから、誰が意思決定して、誰が会社を代表するのかという対外的な責任者の情報が重要であって、会社の内部の序列はあまり重要ではないことになります。
会社の序列は、会社の内部で決めれば済むことなのです。
会社は人間の集団ですので、指揮命令のための序列が必要になってきます。
同じ取締役で経営の意思決定を合議でする役割が同じでも、取締役社長、取締役副社長、取締役専務、取締役常務といった運営のため指揮命令の序列が必要なのです。
ややこしいですが、代表取締役社長、代表取締役副社長、取締役副社長、専務取締役などと言ったいろいろな言い方がありますが、結局は会社法上の機関名と会社の序列を併記していることになります。
役員といった場合、会社法では取締役、代表取締役のことですが、従業員などは専務や常務、部長といった会社内部の序列を表す役職自体を役員といったりもします。
役員の任期、役員変更登記とは
株式会社は会社法の規定で取締役の任期を2年~10年の期間に必ず設定しなければなりません。
ここで注意するのは、任期満了し同じ役員が継続する場合でも役員変更登記が必ず必要になることです。
この任期をうっかり見過ごして役員変更登記しないでいると、登記懈怠(けたい)となり会社法違反事件として100万円以下の過料(行政上の金銭罰)が発生しますので注意が必要です。
登記懈怠(けたい)で過料がかかってしまうケースが多いのが、株式会社の役員変更です。
任期が到来してうっかり見過ごしてしまうことがよくあるのです。
機関の変更とは
会社の運営機関を変更することです。よくあるのは、取締役会設置会社が、取締役の死亡などで取締役3名が必要なところ1名を欠いてしままって、後任者が見つからない場合に取締役会、又は監査役を廃止をする場合があります。
これは登記事項ですので、会社の登記事項証明書を確認すれば、会社の運営機関がわかります。
公開会社と非公開会社とは
株式を何も制限なしで譲渡できる会社を公開会社といいます。上場企業などはその代表例になります。
株式を譲渡するのに、取締役会の承認や株主総会の承認が必要な会社を非公開会社といいます。
同族会社はその代表例になります。
これは登記事項ですので、会社の登記事項証明書で確認できます。
登録免許税とは
会社の変更の登記の種類に応じて、法務局に登録免許税を納める必要があります。
登録免許税には登記の種類により税額の区分があり、同区分の登記の種類を同時に申請する場合は1区分の登録免許税となります。
(例)役員変更と監査役の会計監査役限定登記
ばらばらに登記申請すると2万円になるが、同時に登記申請すれば1万円
(例)商号変更と目的変更
ばらばらに登記申請すると6万円になるが、同時に登記申請すれば3万円
(例)株式譲渡制限の設定と株券不発行。
ばらばらに登記申請すると6万円になるが、同時に登記申請すれば3万円
| 区 分 | 登記の種類 | 登録免許税額 |
| ①役員の事項の変更 | ・取締役・代表取締役・監査役等の重任、就任、辞任の登記 ・代表取締役の住所変更登記 ・監査役の会計監査限定登記 |
申請件数1件につき1万円(ただし、資本の金額が1億円を超える場合は3万円) |
| ②登記事項の変更・廃止に関する事項 | ・商号変更 ・目的変更 ・株券不発行 ・株式譲渡制限の設定、変更 、廃止 ・監査役の設置、廃止 |
申請件数1件につき3万円 |
| ③取締役会・監査役会の事項の変更 | ・取締役会の設置、廃止 ・監査役会の設置、廃止 *「監査役」の設置、廃止は別区分となりますので注意です。 |
申請件数1件につき3万円 |
| ④本店・支店移転の登記 | ・本店移転 ・支店移転 |
本店または支店の数1カ所につき3万円 |
| ⑤会社の解散の登記 | ・解散登記 | 申請件数1件につき3万円 |
| ⑥清算人の選任の登記 | ・清算人選任登記 | 申請件数1件につき9千円 |
| ⑦清算結了の登記 | ・清算結了登記 | 申請件数1件につき2千円 |
| ⑧登記の更正の登記 | ・代表取締役の住所の更正登記 | 申請件数1件につき2万円 |
現在事項証明書とは
以前の変更前の履歴が省略されており、現在有効である部分の登記事項の証明書です。
(商号と本店の一つ前の履歴は現在事項証明書でも記載されます)
全部事項証明書と一部事項証明書がありますが、全部事項証明書を取得するのが一般的です。
上記のことを会社登記簿謄本、会社登記簿抄本といいましたが、今でも一般に使用する言葉です。
履歴事項証明書とは
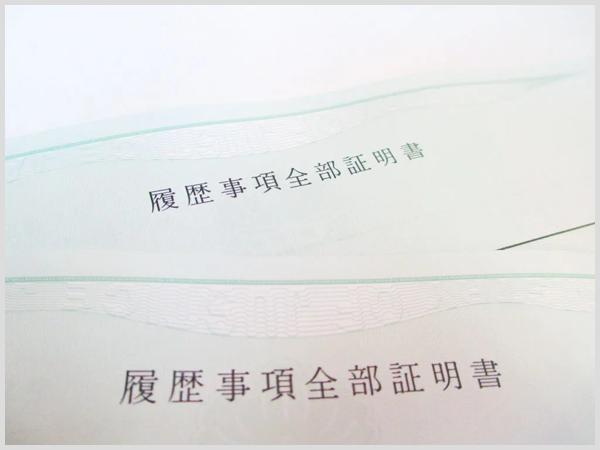
現在有効である登記事項に加えて、以前の変更前の履歴が分かる登記事項証明書です。
(請求日から3年前の日に属する1月1日から請求日までの抹消された登記事項の履歴が記載されます)
どちらを取るか悩んだら、履歴事項全部証明書をとることをお勧めします。
全部事項証明書と一部事項証明書がありますが、全部事項証明書を取得するのが一般的です。
昔は会社謄本・会社登記簿謄本といいましたが、現在でも一般に使用する言葉です。
閉鎖事項証明書とは
履歴事項証明書に出てこない、以前の抹消事項を確認したい場合に取得いたします。